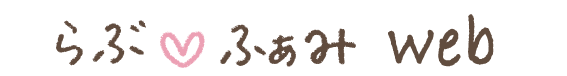4歳と1歳のママ 未来さんの体験談とおうち備蓄
復旧までに電気は約1週間、ガスは1ヶ月以上かかりました

(パパ・ママ・4歳・1歳)
私の実家は、東日本大震災で大きな被害を受けた仙台市若林区にあります。元々地震の多い地域で、私自身も震度5強以上の地震を何度か体験しており、昔から防災に関心がありました。
東日本大震災のとき、私はすでに成人し、家を出て関東にいましたが、地元である仙台市若林区は大きな津波被害を受け、悔しいことに多くの犠牲が出ました。地元にいた友人の中にも、家や大切な人、モノを失った方が少なくありません。
私の実家は浸水こそ免れたものの、ガスと電気が止まり、両親と妹は3月の低い気温の中、家中のロウソクを集めて夜通し火を灯して過ごしたと聞いています。
電気の復旧に約1週間、ガスの復旧に1ヶ月以上。その間お風呂には入れず、お湯を沸かすのには物置にあった石油ストーブを使ったそうです。
普段の生活から防災を意識した行動を心がけています
結婚前から防災用品を揃えていた私ですが、東日本大震災以降、絵に描いた餅のような防災備蓄から、実際の状況を想定した備えをしようと考え方をあらためました。
過去の経験から、災害後も多くの場合は自宅で過ごすことが多いと把握しているので、我が家は主に【災害時に自宅で過ごさなくてはならなくなった場合】を想定した備えをしています。
幸いにも今住んでいるエリアは浸水リスクが低く、おそらく火災が起きない限りは、災害時であっても自宅で過ごす確率が高くなります。
我が家には小さい子どもが2人いるので、ガスコンロ、非常用トイレ、水タンク、備蓄電池、懐中電灯やペンライトを多めに備えています。どれも、ガスや電気などのライフラインが止まってしまったときに最優先で必要になるものです。

在宅避難を想定し、家のいろいろなところに分けて収納しています。
- ウォータータンク
- ガスコンロとボンベ
- 簡易トイレ
- キャンドル
- 非常用水と非常食
- 複数のペンライト
- それ以外のもの
以前は防災の本に書かれているリストを参考にリュックに詰めていたのですが、子どもが産まれてから赤ちゃんを抱っこ紐に入れて、重たい荷物を背負って逃げるのは無理!と気付き、今のスタイルになりました。
その他、普段から気をつけていることは次の3つ。
- 小銭を多めに保管する
- ガソリンは常に満タンを意識する
- 子どものおむつやティッシュペーパーは多めに持っておく
小銭は、実際に被災した友人から「小銭がなくて困った」と聞いたからなのですが、公衆電話や自販機で使えるほか、震災時、限りある商品を届けようと開けてくれたお店は、どこもお釣りがなく大変だったそうです。
ガソリンは、停電しても車でスマホの充電ができる、テレビで情報が得られるといったことから、日頃からの習慣として常に満タンでいられるよう気をつけています。
防災訓練を兼ねておうちピクニックをやってみました!

そろそろ防災用品の点検でもと思い、思いつきで「おうちピクニック」と銘打って家中の明かりを消し、床に大きなブルーシートを敷いて、太巻きや唐揚げを食べました!
4歳の上の子はいつもと違う真っ暗な部屋とお弁当に「ピクニックー!」とウキウキ♪ベルトをつけて椅子に座らされた0歳の子はされるがまま不思議そうでした笑。
みんなで太巻きを食べながら、手回しラジオの電波が実際に入るか確認したり、電池の残量をチェックしたり、、、
もちろんレジャーも兼ねているので、スマートフォンと繋いだ小型スピーカーでキャンプ風BGMを流して、パパは片手にビールを持ちながらキャンプ気分!笑。
今ある懐中電灯やキャンドルだけでは意外と暗くて、あの手この手でランプを吊るしてみたり、赤ちゃんが危なくないように毛布を持ってきて暗闇で見えない危険な場所を防いだりしました。
「やっぱりキャンプ用の電池式のランタンは一つあった方がいいかなあ」と防災用品を見直しつつ、防災訓練をするよい機会になりました。
日本に暮らす以上避けられない災害。
必要以上に恐れずにすむよう、上手につきあっていけたらと思っています。